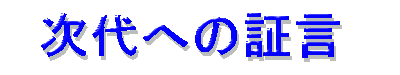終戦前後の私の体験
及川喜代江
日本赤十字社青森県支部に籍があります私に救護看護婦として、青森陸軍病院勤務を命ずるとの召集が届きましたのは、昭和二十年一月十日頃でした。
母の心のこもったささやかな祝膳を囲み、将来南方方面への従軍も考えられるとのことから、これが最後になるかもしれないと別れを告げ、父と共に第二の故郷である小泊村を出発しました。筒井にある陸軍病院は、青森五聯隊の隣に建てられていて、大勢の救護看護婦が陸軍看護婦と共に、傷病兵の看護に当っておりました。私は伝染病棟勤務を命じられましたが、ほとんどが結核患者で、外地からの転送者で占められ、病室はいつも満員でした。軽患者は別として、やせ細った患者達はただ死を待つばかりの状態で、ただ一つの栄養源である少しばかりのバターや玉子の配給を心待ちにしていました。この人達は名誉の召集や入営をして、国のため命を投げ出して戦地などで戦ってきたのです。病床に伏して、どんなにか口惜しい思いをしているかと、出きるだけ親切にし、いきる望みを持つように努めました。
そのうちに内科病棟に勤務替えとなりました。陸軍病院は空襲に備えて、類焼を避けるために総ての渡り廊下は壊され、庭には何ヶ所もの防空壕が掘られ、重症患者は横内小学校に移され、医療器具や医薬品の一部は横内方面に疎開しました。病院内で使用するガラス器具等の在庫品は、将来そのまま使用できるとのことで、庭に穴を掘って埋めたと聞きました。
丁度そのころ樺太の部隊から沖縄の部隊へ行く途中の擬似パラチフス患者100名ほどが収容されました。突然のことで、空き部屋が病室に早替わりして、一時はテンヤワンヤしていましたが、別段、体具合が悪いわけでもなく、さりとて外出もできないし、一日病室でゴロゴロしていたのですが、真性患者が出ないので、一ヶ月ばかりで元気に沖縄へ向けて発っていきました。着いてまもない頃、沖縄陥落の報道に愕然としました。全員玉砕したのかと思うと、やはり直接受け持たされた私にとりましては、真性患者が一人でも出ていたら出発が遅れて玉砕にはならなかったでしょうし、運命と言うものは予め決まっているのであろうかと、つくづく考えさせられたものでした。
そのうち日増しに内地にも空襲が烈しくなり、国民も一戦を交える覚悟で、本土決戦に直結した訓練をと、市内の女学校へ、陸軍病院から一部の軍人達が、救護法やタンカ訓練の指導に派遣されていました。
隣組が竹槍や防火訓練に汗を流している頃、青森市近郊近在の土蔵は白いと言うので敵機の目標になるからと墨を塗ったり、泥を塗ったりして真っ黒な土蔵に化けたようでしたが、陸軍病院でも、白衣は危険とのことで、看護衣、病衣、診察衣など、総ての白衣をヨモギの汁で染め、私達はまだら色したヨモギ衣にモンペを穿き勤務しました。
庭に大鍋を据えて、兵隊や軽患者の採ってきた、たくさんのヨモギを入れて、何日もかかって染め上げました。
青森市の上空にも敵機が現れるようになり、毎日のように警戒警報、空襲警報のサイレンが鳴り、その度に救護班は筒井にある官舎から陸軍病院までかけつけました。病院の炊事班でも、主食にコーリャンが半分以上混じり、野草のおひたしなどを試食させられたのもこの頃でした。
七月十四日に、アメリカ空軍の艦載機による機銃掃射で、野内の石油タンクが燃え何時間も黒煙が上がり、陸上で指揮を執っていた司令官が担ぎこまれた時は片足半分負傷し、直に切断せざるを得ない重傷患者でした。沖では船がやられ、全員海に投げ出され、機関士が大ヤケドを負って運ばれてきたが、心臓が動いているだけで、手の施しようもなく、真夏のことだけにハエを追い払うのが精一杯で、五、六日で絶命されました。たしか東津軽郡出身者だと記憶しております。本当に哀れでした。
空襲の二日ぐらい前だったか前日かに市内に外出していた患者たちが、空からビラが撒かれて、その中に”青森の良民よ、命惜しかったら逃げろ、今に爆撃する”などと書いてあったそうだとか、住民が山の方へ逃げているので、隣組長は配給を分けてやらないとか、帰って来いとか、陸軍病院の中にいても情報は絶えず入ってきました。
私の周りでは誰一人として青森市が爆撃されるなどと思ってもいなかったようでしたし、私達も私物は一切疎開させず押入れに入れておきました。
当夜サイレンの音とともに制服に身をかため、洗面具一つ持たず、いつものようにすぐ戻れるつもりで官舎をあとにしました。
陸軍病院に着いて間もなく、激しいB29の音が聞こえ、暗い夜空が真っ赤に燃え、勤務者も患者も急いで防空壕に身をかくしました。
伝令が飛んできて、「救護班官舎に落されました。目下燃えています」の声に、わが身を疑いました。今出てきたばかりなのに、救護班一同は信じられないと防空壕から身を乗り出してきました。
上官に「もう一度たしかめてこい」と言われ、伝令は引き返していきましたが、本当だったと、二度の報告に留守番の書記殿御夫妻の安否を気遣いながらも、防空壕に当る不気味な音に首をすくめておりました。
やがてB29が去って、勤務者は二班に別れていきました。一班は市内救護に、私は留守班で、手術室で待機しました。負傷者はトラックで運び込まれてきました。
両手が付根からぶら下がっている人、両足切断、顔一面破片だらけの人、お尻が半分もぎ取られてきた娘さんは、病院に着くなり息を引き取りました。
とぼしいローソクの灯りを頼りに、手術は次々と行われ、やがて病院は満員になり、半死半生の負傷者のうめき声が病院中にひろがりました。私達は、もちろん一睡もしないで看護に当りました。
翌朝交代して市内へと出かけました。救護班と隣りの下士官官舎は跡形もなく焼け落ちてしまい、道路を隔てた将校官舎は無事でした。和田寛工場の前を通った時、小山ほどの大豆が何ヶ所かにあって、真っ黒にこげてあたり一面におっていました。
堤橋にでて驚いたことは、一望千里とはこのことかと青森の端から端まで丸見えだったことでした。青森駅も見えたようで、焼け跡の建物も数えてみました。そこ、かしこ一面にくすぶっている中に、焼けトタンをかぶせたピンク色をした死体が何人も折り重なって何個所にもありました。防空壕に逃げた人たちとのことでしたが、蒸し焼きになったのでしょう。地獄とはこのようなものかと思われ、戦争の恐ろしさを嫌というほど、身をもって覚えました。
焼けた衣類が惜しかったと心の奥で残念がって見ましたが、恥ずかしいと思いました。空襲後、陸軍病院も危ないと言うことで、残る患者全員を横内小学校に疎開させ、私もそこの勤務となりました。
八月十五日、天皇陛下の玉音が放送されるとのことで、勤務者全員、ラジオの前に直立不動の姿勢で立ちましたが、お言葉の意味を誰も解せず、これからもがんばるようにと励ましのお言葉であろうと解釈し合いました。勝つまでは。勝つまではといって・・・。
翌日、上官から、日本国は無条件降伏したのだと教えられて呆然として口惜し涙を流し、肩から力が抜けていくのが分かりました。患者もまた泣きました。小学生が来て、学校のまわりや空き地という空地に植えていたヒマ(油をとる)を抜いては投げ、「馬鹿やろう」と叫びあっていました。勉強する暇なく、ヒマシ油をとるため畑作業に明け暮れていたのでしょう。それに松やに取りにも行ったようでした。
終戦後は陸軍病院に戻り、これからの命令を待っていました。
患者たちはそれぞれ故郷に帰されました。
アメリカ軍が上陸してくるとの報に、女性は危険であるから、すぐ故郷に帰るように指示が出され、救護班、陸軍看護婦班ともども陸軍病院を離れることになり、固い握手を交わしながら別れを惜しんだ時の気持ちは、今もって忘れることはできません。
陸軍病院のバスに集団で駅まで運ばれ、十月の末、召集解除の報を受け取りました。
私たちの後、軍人達も次々と故郷に帰り、偉い軍人たちだけが残務整理のために残り、十一月、十二月と全員帰られたと聞きました。
横内に疎開した医療品なども、いっさいアメリカ軍へ渡したということも、後日耳に致しました。また、五聯隊や陸軍病院はアメリカ軍の上陸のため残されたとのこと。
私はその後、結婚生活に入りましたが、同僚達は再度召集されて、久里浜や函館の陸軍病院に二年ほど勤務したそうです。
ちなみに、終戦当時の救護班の婦長殿は野辺地町出身の栃木キミ(現・角鹿)さんで、書記殿御夫妻は避難されて無事だったことをつけ加えさせていただきます。
こうして私の青春時代は終わりました。
当時を思い起して一つ一つ辿りながらしたためましたが、四十二年前が一挙に目前に訪れた感が致し、自然と涙が零れ落ちました。
私は毎年、七月が訪れる度に、あの悲惨な空襲を思いだし、亡くなられた多くの方々のご冥福を祈らずにはいられません。
次代への証言第七集 |