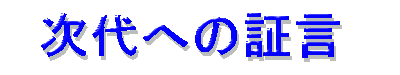赤と黒の思いで
福山正晴
その日、昭和二十年七月二十八日は、家内と私が疎開先の三内どまり。家内の父と妹が古川の家に、その何日か前に仙台の空襲があって、とても「火叩き」、「防水」なぞ、ものの用にもたたないと聞いていたので、私は家内の父と相談の上、荷馬車二台に家財道具をを積んで、三内の知人宅に疎開して、古川の住家には畳二枚だけ残して、仮眠に備えた。義父と義妹、私と家内がペアを組み、夜は古川と三内にそれぞれ起居することとした。この日は、義父と義妹が古川に泊まる日であり、七月に入ってからグラマン機がしばしば青森の上空に現れるようになり、たしか空襲の二日ほど前にも、B29が悠々と青森市の上空に現れ、函館、青森、盛岡、秋田、盛岡なぞの各都市空襲のビラが撒かれ、それが青々とした青田に落下した。拾った者は直ちに警察か憲兵隊に届けるよう・・・とのきついお達しが、新聞にはさまれて、毎戸に届き、何か戦争の末期を思わせる不安が市民の胸をよぎった。
*
二十八日は、何処の家でもラヂオに噛り付き、夕食を終えた。これからの夜に、何か予期しない大事が起こるような、そんな時が刻々と過ぎていった。殆どつけっぱなしのラヂオに警報が入ったのは午後九時過ぎ、「B29の大編隊が鹿島灘より北上せる模様。太平洋、日本海に二手に分かれなお北上中。・・・」と、ガガガ・・・と雑音が入ってラヂオもとまり、異様な雰囲気に包まれた。午後十時をまわって、心なしかB29の爆音を聞いたような錯覚にとらわれ、私は畑に作った防空壕に、女、子供達は入るよう、一緒に疎開していた人々に告げ、せかせてこの人達を収容するのを見届けたのと、ゴワン、ゴワンというB29の爆音の迫る音を聞いたのが、相前後した。私は最後に防空壕の人となったが、二十人程、だまになって入れる壕の中で、「ゴホンベの神様」と、しきりに祈る老婆の声、「婆様。大きい声ださねでけへ、飛行機さ聞こえるハデ・・・」という誰かの声を聞いて、私は、壕から外に出た。市中を圧して、B29が集合するらしく、東西南北をゆるがして、すさまじい轟音が空にあった。相当な数だな──と、胸中をよぎるものがあったが、まだ二十代の私には、それほどの怖さがなかった。北支で実戦の経験があり、生死の岐を何度か味わってきたことと、空襲の未知が、意外に落ち着いた私にしていた。先ず油川のあたりに焼夷弾が落ち、見事な火の幕が降下するのを、夢心地に眺めていたが、その後、直ぐにも轟音は頭上にせまり、風を切る焼夷弾の音が、激しい雨のような音となって、火の幕を浴びせてきた。「来たぞーッ」と、無我の声が、期せずして私の口をつき、野球の心得から、直撃ではないと判断し、「大丈夫だ──」と叫んでいた。弾は防空壕から五十米ほどそれて、人家に命中して、火の手は直に上がったが、二、三軒の被害にとまり、大方は田園にそれたようであった。これが合図のように、青森は市中に火の手が上がり、収拾のつかない火の海と化していった。まさに業火の魔術であった。途方もない大事に、誰もが血を失って、時の過ぎるのをじっと待っていた。
*
翌午前三時、しらじらと夜の明け染めるのも、待ちきれず、私は悲運の泊まり番に当った義父と義妹を案じて、駈けて沖舘を目指していた。まだ余焔のある石川米店のあたりまで一気に駈けぬけ、古川跨線橋前の営林署通りのあたり、川口そば屋の十字路に来て、激しい息苦しさに襲われ、最早進退もままならない状態となった。直感で、線路まで抜けるのと、引き返して石川米店までは同距離と判断し、息をとめたまま、脂汗を流して空き地になる線路まで突走った。酸素の欠乏したこの道は、文字通り生死を賭けた行進であったが、流石に線路に抜けると、潮の香のする空気が美味しかった。ああ助かったという、安堵で、一度に疲労がやってきた。
しかし、まだ青森市は熱のある狂気の街で、とても古川には近づけない状態であり、私は、一応海に出て、一息いれることにした。
そこ、かしこに何人かの人達が一団となって、放心したように乗っていた。誰もが、それぞれの家族達の安否いかぶる顔があった。私も小康のため煙草に火をつけ、ここだけ何事もなかったような海の表情を眺めていた。やがて引き返して跨線橋に上って吃驚した。一望の焼け野原。県庁の一部、蓮華寺がきわだって見え、所々に焼け残った土蔵があるだけで、合浦公園のあたりまで、くすぶる焼煙りに見え隠れしていた。何とも言えない、救われがたい風景がそこにあった。戦争という無残な爪あとを見るおもいが迫ってきた。そこには、人の心を寄せ付けない非情なものがあり、義父と義妹の存命すら疑われて、ひどくわたしは落ち込み、悲観的な気持ちになり、兎に角、現場の家内の実家を訪ねることが重くのしかかり、その反面、早く結果を見届けなければと気があせった。ようやく大気の熱もうすれ、二、三の人々が路上にあるのを見届け、私は家内の実家のあたりを探し求めた。所々にある農業会倉庫とか、僅かに記憶に残る特殊な焼けた器物などでここは酒屋のあったところなどと、手探りのような足取りで、やっと距離感から探し求めた実家の防空壕には誰も居ず、仏壇のあったあたりに、焼夷弾の親玉のようなものが落ちていた。ここまでの間に四、五の焼死体を見て来ただけに、半ば諦めに似た気持ちと、運良く脱出したかという気持ちが交錯して、しばらく周囲を見回して、結局結果自然になるという結論を得て、帰路についた。義父は六十の坂を越えていたし、義妹は二十歳前であったので、多分親子連れ立って、何処かに逃げ去ったものと思い、無事を祈りながら、周辺をゆっくり眺めやる心の落ち着きを取り戻していた。来る時は気づかなかった跨線橋西十字路の川口そば屋附近には、逃げ遅れた焼死体がごろごろあって、一応みとどける余裕もでてきた。
三内では、父と妹の生死を案ずる家内が、待ちきれずに、一時間も前から国道七号線、安生院のあたりまで出ていて、足しげく出入りする人々に鋭い目を注いでいたので、野戦郵便局従軍スタイルの私の格好はすぐ判り、小走りに駈けよって、すぐに「どうだった」と問いかけた。「ん。父さんもR子も居なかった。きっと脱出したと思う。ひょっとすると三内まで来てるかも・・・」となり、連れ立って、疎開先に足を早めたが、午前中は何の徴候もなく不安の内に過ぎた。正午過ぎになって、義妹が無事帰ってきた。せかせかと、父さんはどうしたと聞く家内に、「あれッ、まだ来てねだが─」と妹は呑気なことを言った。とに角空襲の声で、親子は大野方面に向って脱出し、人々に交じって、そのうち離れ離れになってしまったが、多分生きている筈とのこと。妹は炊き出しの握り飯なぞ食べて、ゆっくり帰ってきたので、父は既に帰っているものと思ったらしい。
そんなことがあり、それから一週間は、誰もが虚脱状態の中にあって、何も手につかなかったが、やがて、後片付けに立ち上がり、新しい生活への幕始めが始まった。それにしても、焼け跡の黒々とした木々の匂いは、いまも尚鼻につき、戦争という、呪わしい不幸の中から拾った空襲という経験を経て、やっと握った平和こそ、生涯守り抜かねばと思う。
次代への証言第十三集 |